
~Introduction~
スキャンダルの主犯は、ときに、音楽だった。
1909年、パリ。
天才プロデューサー・ディアギレフが興した
「バレエ・リュス(Ballets Russes)」は、
空前の大センセーションをもたらした。
それは単なる流行のダンス・カンパニーと呼べるものではなかった。
台本。舞台美術。ポスター。衣装デザイン。
時代のトップを走るアーティストたちが集結し、
ときに犯行計画を練るような仄暗い情熱に身を焦がしながら
新作を生み出していった。
*
音楽も、また、例外ではない。
ストラヴィンスキー。ドビュッシー。ラヴェル。プロコフィエフ。
バレエ・リュスに参加した同時代の音楽家たちは
ただ単に、振付師の求めるままに曲を書いたわけではない。
バレエ・リュスの歴史のなかで…いや、人類の全芸術史のなかでも
最大のスキャンダルに数えられる「春の祭典」のアイデアは、
他ならぬ、ストラヴィンスキー自身が持ち込んだものだと伝えられている。
それだけではない。
ショパン。あるいはシューマン。
前世紀に書かれた、しかも本来は踊るための音楽ではない
古めかしく愛らしいメロディまでもが、
バレエ・リュスのコンセプトの魔力にかかり、
思いがけない「犯行」へと昇華された。
*
このアルバムで取り上げられている、
バレエ・リュスの代表作である30作品は、
音楽がもたらした30の罪深く輝かしいスキャンダルの
痕跡であるともいえるだろう。
解説はこちら
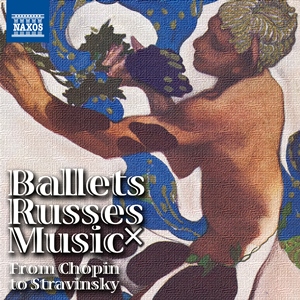
■ 商品タイトル:
バレエ・リュス×音楽 30の共犯関係 – ショパンからストラヴィンスキーまで
■ 税込価格:
1200円(配信/iTunes)
■ 発売日:
2014年8月6日
● ダウンロードはこちらから


■ 収録楽曲:
アルバム解説
「バレエ・リュス×音楽 – なぜ、バレエにおいて、音楽や音楽家が主犯になりえたか」

「牧神の午後」(1912年)バクストの画によるポスター
~バレエ・リュス(Ballets Russes)とは~
1909年~1929年、パリを拠点に一世を風靡したバレエ・カンパニー。
名は「ロシア・バレエ」の意味。その名の通り、主宰者のセルゲイ・ディアギレフを中心に、
ロシア人を中心としたメンバーにより活動を開始。
しだいに在住フランス人アーティストも巻き込み、アヴァンギャルドな色合いを強めていく。
ニジンスキー(ダンサー)、フォーキン(振付師)、ストラヴィンスキー(音楽家)、
ピカソ(画家)、コクトー(作家)などを制作の一員とし、わずか21年の活動期間の中で、
ダンス、音楽、美術に至るまで、アート界全体に多大なインパクトをもたらし、
20世紀芸術の方向性を決定づける。
●「ハルサイ」スキャンダルの主犯はストラヴィンスキーだった?

イーゴリ・ストラヴィンスキー
1913年5月29日。
それは、バレエ・リュスの歴史のなかで…いや、人類の全芸術史のなかでも
最大のスキャンダルに数えられる、とある演目の初演日であった。
「春の祭典」(Tr.15)。
その日、観客は混乱し、罵り合い、ついには暴動さながらの騒ぎに
発展したと伝えられている。
かようなスキャンダルを生んだのは果たして誰だったか。
振付を担当した天才ダンサー・ニジンスキーか。舞台美術家のレーリヒか。
若い学生やアーティストに無料チケットを配り、
騒ぎにわざと火をつけたプロデューサー・ディアギレフか。
全員が、多かれ少なかれ、共犯者であったことはいうまでもない。
──だが、このバレエが誕生したそもそものきっかけにまでさかのぼるなら。
その主犯は、──「音楽」であり「音楽家」であった。
イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)。
彼は自伝でこう述べている。
──「火の鳥」(Tr.7)の仕上げをしていたとき、ふいに新しい
アイデアが浮かんだ。異教の祭典、そして生贄に弄ばれた処女の死──、と。
それはまさに「春の祭典」のコンセプトそのもの。
彼はこのアイデアを、ディアギレフや「バレエ・リュス」の主要メンバーらに提案。
その結果が、このスキャンダラスな初演を生んだのである。
*
実は、ストラヴィンスキーにとって、
「ハルサイ」は、決して“初犯”ではなかった。
さかのぼること2年前。
1911年に初演された「ペトルーシュカ」(Tr.10)。
これもまた、彼自身が考えたアイデアをカンパニーに持ち込んだところ、
メンバーのひとりである舞台美術家のブノワが強く興味を示し、
ふたり共同で台本を書きあげ、作品の制作に至った作品である。
つまり、音楽家が他の分野のアーティストたちを率い、
自ら”主犯格”になることによって、
これらの作品は形作られていったのである。
●なぜ、バレエにおいて、音楽や音楽家が主犯になりえたか

バクストによる「火の鳥」(1910年)の衣装デザイン
それは、これまでのバレエ作品には到底ありえない創作プロセスであった。
なぜなら、バレエの主体は(当然ながら)バレエであり、
音楽は、衣装や舞台美術と同じく、ダンスにちょっとした彩りをもたらす程度の
添え物でしかなかったからだ。
たとえばロマンティック・バレエの代表作「ジゼル」(Tr.6)。
たいへんな多作家であり、50曲以上のオペラやバレエを
書き残したアドルフ・アダン(1803-1856)にとっては、この作品もまた
あらかじめ劇場から求められた依頼に応じて、職人技で
書き上げたものの1つに過ぎなかった。
ディエギレフも深く敬愛した巨匠、
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)でさえそれは決して例外ではない。
彼はその音楽の質の圧倒的な高さによって、バレエ音楽の地位を飛躍的に向上させた。
それでも作曲の折には、振付師マリウス・プティパの意向に全面的に従い、
各シーンごとに、小節数、さらには「ここでトレモロ」「ここで半音階」などの
非常に細々した注文に応じていかねばならなかった。
三大バレエのひとつ「眠れる森の美女」(Tr.26)も、そうした作品のひとつである。
*
ディアギレフは、そうした旧来のやり方とはまったく違う、
新たな作品づくりの手法を編み出すことによって、
結果的に、バレエと音楽の関係性を根本からくつがえした。
彼は、振付師やダンサーのみならず、音楽家、美術家、作家など
カンパニーに携わるあらゆるアーティストに発言権を与え、
彼らのアイデアや、それを共有することから生まれる
新たなコラボレーションを推奨した。
音楽家が台本にかかわり、美術家がアイデアを持ち込み、
ダンサーが舞台美術に口を出す、ということもしばしばであった。
こうした自由な空気の中で、ストラヴィンスキーというひとりの若手音楽家が、
その才能を開花させ、自らバレエ作品の担い手となるに至ったのである。
ディアギレフは、ストラヴィンスキーの斬新なアイデアに常に耳を傾け、
プロデューサーの手腕を最大限に発揮して、それを作品に昇華させた。
もちろん、音楽がバレエ作品の主体になることにより、
そこには新たな苦労も生まれた。
ストラヴィンスキーは、天才的なダンサーでありながら
音楽の基礎を心得ていないニジンスキーに、根気よく
自分の作品の独特な拍子の取り方を教えこみ、
ようやく「春の祭典」の初演にこぎつけたようである。
それまでの合理的な創作スタイルとはほど遠いものであった。
しかしそうした、火花を散らすような切磋琢磨のなかで、
それまでの限界を超えたバレエ作品が次々と生まれたのである。
●ディアギレフと音楽とのかかわり

セルゲイ・ディアギレフ
それまでは、ダンスのための飾りのひとつにすぎなかった音楽を、
ディアギレフが、アーティスト集団の利点を生かす創作手法により
「主犯」の域にまで押し上げたのは、
彼自身の音楽への愛着に由来するところが大きい。
セルゲイ・ディアギレフ(1872-1929)。
彼は自らを「自分では何もできない男」と皮肉る。
確かに彼は、音楽、美術、ダンス、どのジャンルをとっても
プロ並みの実践力を持つ人間ではない。
ただ、彼にはその全てを熟知し、またその全てを束ねてひとつの世界を作り上げる
比類のない統率力を備えていた。
美術への造詣も深く、「芸術世界」という雑誌を立ち上げたほどであったが、
音楽は、彼の人生の中で、別格といってよい存在であったようである。
彼は、毎週のように自宅で音楽サロンが催される家庭で育ち、
チャイコフスキーと遠戚関係であっただけでなく、
「シェエラザード」(Tr.5)「サドコ」(Tr.9)「金鶏」(Tr.18)など
のちにバレエ・リュスのいくつかの作品で登場することになる
ニコライ・アンドレイェヴィチ・リムスキー=コルサコフ(1844-1908)の弟子でもあった。
ディアギレフが、パリに出て最初に手がけたプロデューサーとしての仕事は、
ダンスではなく、音楽であった。
「現代ロシア音楽の夕べ」と名付けられたその定期イベントでは、
第1回バレエ・リュス公演でも取り上げられた
ボロディンの「イーゴリ公」(Tr.2)が演奏され、
また、若き日のストラヴィンスキーがピアニストとして参加している。
*
こうしたバックグラウンドがあってこそ、彼は、音楽の持つパワーを誰よりもよく知り、
当時やや下火になりかけていた「バレエ」という芸術ジャンルへの
新たな起爆剤となることの期待を託したに違いない。
●バレエ・リュスの音楽の多様性
さて、バレエ・リュス作品の音楽といえば、先に紹介した「春の祭典」をはじめとした、
アヴァンギャルドな「書き下ろし」をイメージすることが多い。
しかし、実際には、同時代やひと世代前の作曲家の既存の作品、
あるいははるか昔の作曲家の作品を起用することも多々あった。
その理由は、経済事情やその場の個々のいきさつによるところが大きい。
たとえば、1909年の第1回バレエ・リュス公演の演目のひとつである
「アルミードの館」(Tr.1)は、
1901年にすでにニコライ・ニコラエヴィチ・チェレプニン(1873-1945)によって
書かれていたものの、芸術界の内紛により
放置されてしまった気の毒な曲に、振付師フォーキンが目を留め、
陽の目を見るに至ったものである。
*
昔ながらのバレエの再演も何度か行っており、ここでは
原曲がそのまま用いられることが多かった。
「ジゼル」(Tr.6)の再演は、当時バレエ・リュスに関わっていた
名ダンサーのアンナ・パブロワを、パリで売り出すためであったといわれている。
また「眠れる森の美女(眠り姫)」(Tr.26)の再演は
ちょうど財政の危機にさらされていた1920年代、カンパニーの安定した黒字化を
目指すべく行われたといわれている。
これらの古めかしいバレエ音楽も、バレエ・リュスならではの
新奇な振付や衣装や美術にくるまれて舞台に乗ることにより、
アンビバレントな輝きを宿したことだろう。
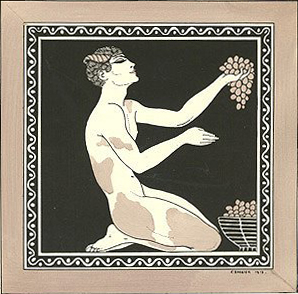
「牧神の午後」(1912年)
ラストシーンの性的な描写がスキャンダルを巻き起こした「牧神の午後」は、
クロード・ドビュッシー(1862-1918)が18年前に書いた「牧神の午後への前奏曲」(Tr.12)の
使用許可を得て、1912年に初演されたもので、
当時すでに、芸術通なら誰もが知っているほどのメジャーな曲であった。
評判の高い現役の音楽作品が、スキャンダラスなテーマ性をほどこされて
舞台に乗ることは、完全な新作とはまた異なる衝撃をもたらしたに違いない。

「レ・シルフィード」(1909年)
1世紀近く前のロマン派の音楽家の作品が
登場することもあった。
ロベルト・シューマン(1810-1856)のピアノ曲集「カルナヴァル(謝肉祭)」(Tr.4)や
「蝶々」(Tr.17)は、19世紀の旧き良き市民時代を伝える
ノスタルジックな作品として、バレエ・リュスの公演に登場した。
ポロネーズをはじめとするフレデリック・ショパン(1810-1849)のピアノ作品は、
アレクサンドル・グラズノフ(1865-1936)のオーケストレーションにより
「レ・シルフィード(ショピニアーナ)」(Tr.3)という名のバレエ作品に姿を変えた。
空気の精(シルフィード)と若者が可憐に舞い踊る姿は、一見、
悲劇のロマンティック・バレエ「ジゼル」にそっくりだが、
その実態は似て非なるものであった。
「ストーリーのない純粋で抽象的な美」を目指したとされる
この作品の本質に、もともと固有のストーリーをもたないショパンの音楽は、
限りなく近いものであったといえるだろう。
かくして、音楽は、バレエ・リュスの舞台の上で、
現代芸術への扉を開いたのである。
*
このアルバムに収録された30曲の音楽の多様性は、
バレエ・リュスが音楽に求めたもの、また音楽がバレエ・リュスに求めたものの
多様性そのものであり、
彼らがバレエ作品の創作を介して、いかにスリリングな”共犯関係”を紡いだかということの
大きな証明であるといえるだろう。
<主要参考文献>
・「ディアギレフ 芸術に捧げた生涯」(著:シェング・スヘイエン/訳:鈴木晶/みすず書房)
・「新版 ダンス・ハンドブック」(編:ダンスマガジン/新書館)
・「魅惑のコスチューム バレエ・リュス展 展覧会カタログ」(新国立美術館)
・「作曲家別 名曲解説ライブラリー チャイコフスキー」(音楽之友社)
※画像は全てwikipediaのパブリック・ドメインです。